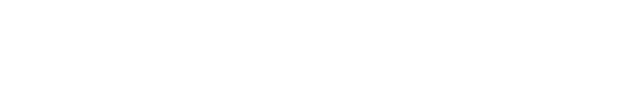治療方針について
1)頚部背部痛
a)神経症状(神経痛)を伴うもの
鎮痛剤(特に神経障害性疼痛治療剤)の内服が主体となりますので、内服の要領を指導いたします。神経痛が落ち着いた時点で再発予防を目的にモーターコントロールの修正を図ります。
b)神経症状を伴わないもの
神経症状を伴わない頚部・背部痛を認めた時点で脊柱(頸椎・胸椎)-胸郭-肩甲帯のモーターコントロールの障害を生じています。治療としては痛みが強い場合は投薬、トリガーポイント注射と物理療法を併用し鎮痛を図ったうえで運動器リハビリテーションにて脊柱(頸椎・胸椎)-胸郭-肩甲帯のモーターコントロール障害の修正を図ります。特に長時間のコンピューター作業等、事務作業の多い女性は脊柱-胸郭-肩甲帯周囲の筋量(筋力ではありません)に問題があることが多くタンパク質摂取を中心とした栄養管理は必須となります。また治療に時間がかかる方も多い部位ですが、最後までお付き合いいたします。
2)肩関節痛
代表疾患は肩関節周囲炎(いわゆる五十肩・四十肩)ですが、なぜか、肩関節痛は放置される方が多いのが現状のようです。痛み、運動障害(背中に手が届かないなど)の症状がでれば、早期(可能なら一か月以内)に受診していただき、早くから治療を開始することで治療期間の短縮に繋がります。症状が現れた時点で肩周囲のモーターコントロールはすでに崩れており、病態が悪化し、肩関節拘縮(靭帯の短縮)を生じてしまうと治療が長期化してしまうことが多い関節です。検査としては超音波検査が有用であり、五十肩と思っていても実は肩腱板断裂(肩の重要な腱の断裂)であった症例は多いものです。超音波を用いると腱板断裂の有無(※1)は数分で診断できます。肩疾患の治療は鎮痛目的に物理療法、投薬、トリガーポイント注射、ヒアルロン酸関節注射を組み合わせて行います。モーターコントロールの障害が強い場合は運動器リハビリテーションの適応となります。
(※1)必要であれば他病院への紹介(手術を要することもあります)
3)腰痛
a)神経症状(神経痛)症状を伴うもの
鎮痛剤(特に神経障害性疼痛治療薬)の服薬指導、トリガーポイント注射の併用が効果的です。痛みが強いときは大変ですが、激痛は症例の8割で約1か月程度で落ち着き、日常生活の支障は約4か月程度でなくなることが多いです。腰椎-骨盤-股関節のモーターコントロールの障害が強い場合は運動器リハビリテーションの適応となります。
b)神経症状を伴わないもの
最も多い症状です。症状がある時点ですでに腰椎-骨盤-股関節のモーターコントロールの障害が生じています。腰痛が投薬などで一旦落ち着いても腰痛を繰り返すことが多いのは上記モーターコントロールの障害が修正されていないためです。急性痛が強い場合は服薬指導、トリガーポイント注射(効果的です)を行います。急性痛が落ち着いた時点で運動器リハビリテーションにて腰椎-骨盤-股関節のモーターコントロールの修正を図ります。
4)股関節周囲痛
近年増加している印象があります。股関節インピジメント症候群、変形性股関節症が代表疾患ですが、MRI 検査で精査すると股関節に水腫が溜まっている例は意外と多いようです。レントゲンに問題が見られない場合は比較的診断が難しい部位でありMRIが必要となることが多い関節です。
※当院ではMRI 検査ができませんので近くの病院に予約を取って検査を受けていただいております。
a)股関節インピンジメント症候群
大腿骨頚部(付け根)と寛骨臼蓋(骨盤の関節の縁)が衝突して発生します。腰椎-骨盤-股関節のモーターコントロールの改善を図る必要あり運動器リハビリテーションは必須となります。
b)変形性股関節症
変形は進行性であることが多く、予防的な運動を含め経過観察が必要です。また、必要であれば手術療法の検討も必要です。障害のベースに腰椎-骨盤-股関節のモーターコントロールの障害が存在しますので運動器リハビリテーションの良い適応です。
5)膝関節痛
初発症状として膝裏の痛みがあります。膝裏に痛みがある場合は股関節-膝関節-足関節のモーターコントロールは障害されています。当院において膝裏の痛みを訴えた方の17% にベーカー嚢腫(膝の裏に水がたまる)を認めています。ベーカー嚢腫の有無や膝周囲筋のモーターコントロール状態を把握するのには、超音波検査が非常に有用です。治療としては物理療法をはじめとして、痛みが強い場合は注射療法(トリガーポイント注射、ヒアルロン酸関節注射)、股関節-膝関節-足関節のモーターコントロール修正のための運動器リハビリテーションを主体としています。いわゆる鎮痛剤の内服のみで終わりではなく、運動指導などによる自身の管理が必要となる疾患です。
6)スポーツ障害
当院にて積極的に治療を行っております。いわゆる使い過ぎ(over use 症候群)で障害を起こしていると思われていますが、モーターコントロールの破綻がベースとして存在していることがほとんどです。このモーターコントロールの障害を見つけ出し、修正を図らない限り根本的な治療を行うことが出来ません。障害部位の鎮痛をスポーツ障害治療のゴールとして考えていると、いったん除痛が図れてもその後、再発や関連部位の障害を来すことが多いです。時間をかけてでもモーターコントロールの修正を図るべきで、モーターコントロールの修正が図れれば障害を起こしにくい体とパフォーマンスの向上を同時に手に入れることが可能となります。患者様自身にモーターコントロールの障害を自覚していただくことが治療の近道になります。やみくもに練習を行ってもモーターコントロールに障害が残っていれば症状として発現してきます。努力は裏切らないとよく言われていますが、やみくもな努力(練習)は簡単に本人を裏切ります。これは努力自体を否定するものではなく努力の仕方の問題です。
当院では運動器リハビリテーションをメインとしてモーターコントロールの修正を図っていきます。裏切らない筋肉(体)の作り方を指導させて頂いています。努力するのは本人の責任、努力の方向性を示すのが治療者の責任です。
モーターコントロール(運動制御)とは
当院で考えるモーターコントロールとは、運動動作において効率よく動作を行えるように制御を行う能力と考えています。決して筋力(パワー)があれば運動がうまくなるとは考えておりません。動作を行う際に体は単一の部位だけで行っているわけではなく、必ず共同で働く部位(共同運動・シナジー)があります。この共同運動をコントロールする能力が重要になります。共同運動が障害されたまま動作を行うと動作の正確性は低下し応力が集中したところに障害を生じてきます。これがモーターコントロールの破綻による障害です。共同運動の障害は肉体的・精神的疲労にて簡単に引き起こされてきます。これがやみくもな努力(練習)は簡単に本人を裏切る理由です。モーターコントロールの障害はスポーツのみならず、生活習慣でも引き起こされます。これが整形外科疾患のベースとなっています。